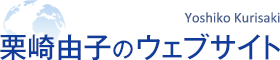30年ぶりに戻ったら (150) — 言葉がわからないという不安
【言葉は生きる力だと気づかされたある経験】
連日、テレビでも新聞でもコロナウィルスのニュース報道が続く。
知るべきことだと思うが、正直に言って怖いニュースばかりに接していると、もう聴きたくないなあ、と思うこともある。
「だけど、、」と一歩引いて考える。
怖い、もうたくさんだ、と思うのは、わたしが報道される言葉を理解できるからた。
これがほとんど理解できなかったら、どれほど不安だろうか。
そう気づいたとき、オランダで似た経験をしたことを思いだした。
アムステルダムから長距離列車に乗って、片道3時間ほどかかる街に留学していた友人を訪ねたときのこと。朝7時頃の列車で目的地の街に行き、友人と軽い昼食を一緒にする。その後とんぼ返りでアムステルダムの空港に引き返し、その日の最終のフライトでジュネーブに帰る、という日程だった。
オランダは交通大国だから、列車は時間通りに動くだろうと思っていた。
また、わたしはオランダ語は分からないけれど、オランダの旅に不安を持ったことは一度も無かった。先ず殆どと言っていいぐらい、人々は英語を話す国だからだ。
その安心と、1日の終わりに宿に戻るのではなく、フライトに間に合わなければならないという旅程を組んだことがわたしの油断だった。
途中の駅で列車が止まった。
車内アナウンスがわからない!
オランダ語だけ!英語の放送はない。え、このオランダで?!しかも、アナウンスの音質は声が割れてとても悪かった。
周りに人はいない。ガラガラの列車。
社内を歩いて、離れた席の人に何が起きているか英語で尋ねたが、その人にも分からないという。
この後のフライトに乗れないと困るのだ!それはジュネーブ行きの最終便だから!!!
わたしは列車を降りて、長いプラットフォームを歩いた。駅員を探すために。
それがなかなきないのだ、こういうときには!
結局、わたしは列車を乗り換えてアムステルダムまで戻り、もう一度乗り換えて、スキポール空港に着いた。最終便には間に合った。
今日本に住む外国の人々や留学生野中には、日本語が十分に分からない人々が大勢いる。ネットにアクセスできない人々もいるだろう。
そういう人たちの不安を思うと胸が痛む。
これはどちらが良い悪いという話ではありません。世界はこんなもんだということで。

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
学びのポイント: 自分の住む土地の言葉を話せるようになろう。もし日本に住んでいるなら、「やさしいにほんご」を知って、誰かのために役立てよう。
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
- おなじテーマの人気記事はこちらです→
- 欧州生活30年の経験をもとに、講演、セミナー、執筆、取材を致します。テーマは多文化共生、お互いの違いを資源にするには?など。