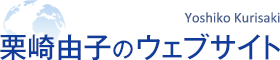30年ぶりに戻ったら (145) — お弁当に潜む文化ギャップ
【いたずら小僧を捕まえた!】
こんな光景が好きだ(写真)。ある日の昼時、上野公園で見た光景である。

野外で円陣を作ってお弁当を使う(少し古い言葉だが、お弁当は”使う”と言った)。日本の人々は老いも若きも、こんなことを本当にごく自然に行う。
いいなーー。
その数日後、
夕方から始まったある研修会場で、お弁当が出された。その時のことだ。
(わたし)「お弁当は日本にしかないわ、いいわーー。」
(A子さん)「あら、最近は外国でもベントウという言葉は通じるんでしょ?」
A子さん、素敵な思い違いをありがとう!ーー口には出さなかったがわたしは内心「いたずら小僧を捕まえた!」と思って喜んだ。
そのいたずら小僧は目に見えない。それもそのはず、その名は「文化」。人それぞれの文化の中での思い込み、そのズレが意識の小さな落とし穴となって会話の中に潜んでいる。そして本人たちは気付かない。
A子さん、違うのよ!
ベントウという同じ言葉を口にしながらも、日本人とそうでない人の頭に思い描く映像は全く別物なんだから。
わたしにはこんな経験がある。
ジュネーブの美術館の友の会事務局で働いていたときのこと。
IT 担当のモニカが、会員情報を「ベントー」に入力してね、とわたしに言う。
は?
なんと、ベントウとは、CRM (Customer Relationship Management)つまり 顧客管理ソフトのことだった!そして、それはフランス語のソフトウェアである。
わたしの想像だが、ベントウという名前が付いたわけは、きっとこうだ。そのソフトには、個々の会員の住所、会員歴、家族構成、会費支払い履歴etc. 多種の情報が一枚のシートに整理されて記録されている。まるで、一つの箱に多種のおかずを詰めるお弁当のように。
ベントウがこんなソフトウェアを意味する人々にとって、わたしが上野公園で目にしたような光景はきっと説明のしようがないだろう。
これはどちらが良い悪いという話ではありません。世界はこんなもんだということで。
(写真、上野公園)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
学びのポイント: 同じ単語を使っているからと言って、その意味することが同じことは、まずない、と思って間違いないのが、異文化コミュニケーションの心構えだ。家族、チームワーク、学校、etc. 枚挙に暇ない。だから、異文化を知ることは計り知れないほど面白い。
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
- おなじテーマの人気記事はこちらです→
- 欧州生活30年の経験をもとに、講演、セミナー、執筆、取材を致します。テーマは国際ビジネスにひそむ見えない文化ギャップ、多文化共生、など。