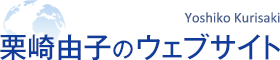30年ぶりに戻ったら (133) — 交渉力と想定外
【ヨーロッパ生活で身につけたもの】
3年前の今日はこうだったと、フェースブックが思い出させてくれた。ジュネーブから日本に一時帰国する際のことだ↓↓↓
2016年12月7日
まさかのフライトドタキャン✈️!チェックインの後だけにフライト変更だけでなく荷物の引き取りもあり。アレコレと2時間ジュネーブ空港を3周。これで3000歩!今ひとりビール🍺でご苦労さん会をやってる空港のカフェです。ANAがAir France に。3時間遅れたって羽田には着く、廊下側の座席もやり直しのチェックインで粘ってゲット。おーエアフランスならエコノミークラスでもシャンパン飲める🍾わたし、よくやった。土壇場の瞬発力を自分で讃えて楽しい11時間を過ごそーと。お友達の皆さま、もうすぐお会いしましょう。
自分の得たいものを得るために粘って交渉する力、
何か想定外が起きたら目の前にある確実なことに目を向けて切り抜けるという現実感覚、
確かにこういうものはヨーロッパ暮らしで身につけたと思う。
私の経験の範囲だが、ヨーロッパではいろいろなことがかなり交渉できるのだ。大学のレポート提出期限を延ばして貰う、列車が遅れたために接続の最終列車に間に合わず、被ったタクシー代を鉄道会社に払って貰う、など、交渉の機会は日常生活のあらゆる襞に潜んでいる。
親は子どもに「粘りなさい」「交渉しなさい」と教えて育てる。
交渉される方も、そんなものだと思っている。
規則にばかり頼っていないのだ、社会の仕組みそのものが。それがある種の柔軟さを人々の頭に生み出している。
日本にいるとこういうチカラを身につける機会はなかなか無いのではないか?
例えば日本だと、交渉してもどうにもならないことが多い。規則で決まっている、の一点張りなのだ。最近の例はわたしにとって全く納得のいかない銀行の手数料。
良くも悪くも、日本では想定外のことは起きにくい、または起きないことになっている。細かな規則が敷かれていて、人はそれを従順に守るよう、しつけられている。規則にないことは、現実に無いことにされるか、「あなたは例外です」で片付けられるかのどちらかが大半のようである。規則が現実に合わない、という発想は希だ。
だからこそ、想定できない事故や自然災害の対応がどんなに大変か、想像を超えるのだが。
これはどちらが良い悪いという話ではありません。世界はこんなもんだということで。

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
学びのポイント: 今日は何か交渉できることが無いか、身の回りを探してみよう。無意識の決めつけや諦めを外すと、案外見つかるものだ。
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
- おなじテーマの人気記事はこちらです→
- 欧州生活30年の経験をもとに、講演、セミナー、執筆、取材を致します。テーマは多文化共生、お互いの違いを資源にするには?など。